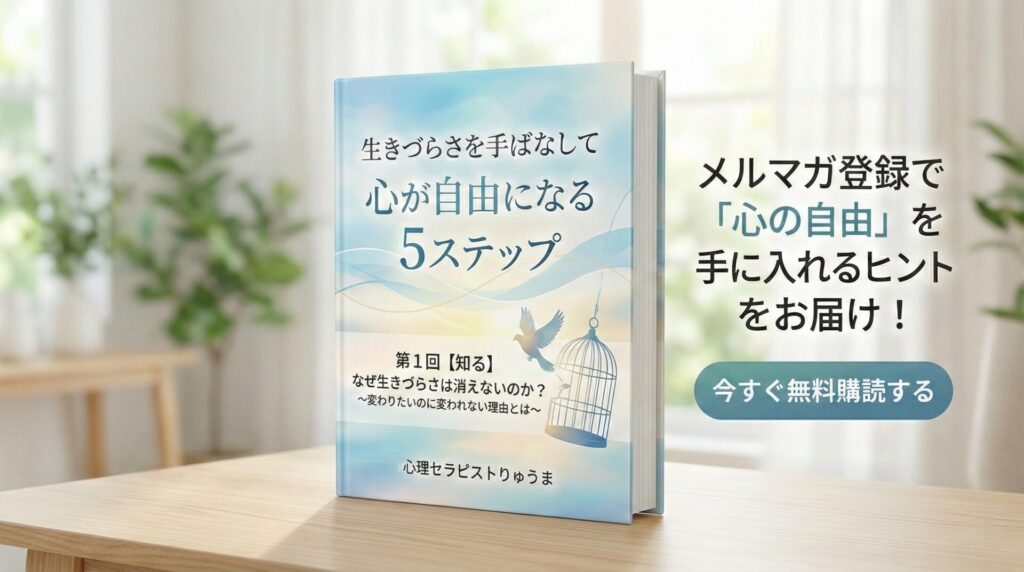なんでこの人、あんなに自信満々なんだろう?
どうして話が通じないの?
そんなふうに感じたことはありませんか?
人間関係に問題を抱え、こじらせている人には、共通した特徴があります。
そのひとつが、
「自分はわかっている・できている」という思い込みを持っていることです。
この思い込みが、本人も気づかないうちに人間関係に悪影響を及ぼしているのをよく見かけます。
今回は、その背景にある心理現象、「ダニング・クルーガー効果」について、人間関係への影響を交えてお話しします。
「ダニング・クルーガー効果」とは?
ダニング・クルーガー効果とは、ある特定の分野において能力の限られた人が、自分の能力を過大評価してしまうという認知バイアスのことです。
簡単に言えば、
能力が低い人ほど、自分の能力を過大評価しやすい
逆に、能力が高い人ほど、自分を過小評価しやすい
という認知の歪みのことです。
たとえば、運転がうまくないのに「自分は完璧に運転できている」と思い込んでいる人、
逆にすごく丁寧に仕事をしているのに「自分なんてまだまだ」と自信を持てない人、
あなたの周りにも思い当たる人がいるかもしれません。
「わかってるつもり」が人間関係を壊す
この効果が人間関係に及ぼす影響は、意外と大きいです。
特に多いのが、こんな場面。
• 職場で「俺のほうが経験あるから」とマウントを取る上司
• 家庭で「あなたはわかってない・できない」と決めつけるパートナー
• 恋愛関係で「こうすればうまくいく」と一方的にアドバイスしてくる人
こうした言動の裏にあるのは、
「自分は物事をよくわかっている」という
思い込み
そして、
「自分は正しい、あなたは間違っている」という
勘違いです。
でも実際は、相手の気持ちや状況をきちんと見ていないことが、現実であることが多いです。
本当にわかっている人は、静かに悩む
逆に、すごく繊細で優秀な人ほど、こう言います。
「自分はまだまだです」
「私なんかが意見していいのかな」
能力がある人ほど、自分の足りなさに気づける。
多くのことを学び、知っている人ほど、
「自分にはまだまだわからないことがある。できないこともたくさんある」
ということを知っているのです。
だからこそ、声を上げにくくなってしまったり、自信が持てない、ということが往々にしてあります。
ちなみにモラハラは、「自分は素晴らしい」と勘違いした自信過剰な人が加害者になり、
「自分には足りないところがある」と考えて自分を過小評価する人が被害者になりやすいです。
心理セラピーを通して見えてきた、あたたかい関係に必要なこと
私が心理セラピストとして日々感じるのは、
自分と相反する考えを受け入れられる人
つまり、葛藤を受け入れられる人ほど、他者と深くつながれる
ということです。
自分と違う価値観や考えを持つ人に対して、
「あなたはそうなんだね」
と受け入れられる人は、人間関係うまくいきやすい。
私自身、心理セラピーのセッションをするときは、クライアントさんの問題は「こうに違いない」と決めつけないように、
「わからないから聞いてみよう」
という姿勢で、クライアントさんと関わるように気をつけています。
人のことをわかった気になるのは、傲慢というものです。
心理学を学んだりすると、勘違いしやすくなるんですよね。
「自分は人の心がわかる」と。
でも、そう思っている時点で勘違いなんです。
人の心はわからない。
できることは、話を聞いて、見て、感じて、想像することだけ。
日常の人間関係でも同じです。
「私はこう感じたけど、あなたはどう?」
「もしかしたら違ってるかもしれないけど、聞かせてほしい」
そんなふうに、自分の考えを絶対視しない姿勢が、相手との信頼を深めてくれると思っています。
あたたかい人間関係を築くために
ダニング・クルーガー効果は、誰にでも起こりえます。
大切なのは、「自分が正しいとは限らない」という視点を持つこと。
もし、人間関係でモヤモヤすることがあったなら、
「自分はわかっている・できている」という“つもり”になっていなかったか?
「相手も何か思うところがあるかもしれない」と相手の視点を持つことはできるているか?
少し立ち止まって、見直してみましょう。
ダニング・クルーガー効果は、人間関係にも気づかないうちに影響を与える認知の歪みです。
わかっている“つもり”、できている“つもり”が、人間関係を壊してしまうこともあります。
でも、「わからない」「できないかも」と言えることが、関係を深めるきっかけになることもあります。
あなたの中にある、わかっている“つもり”、できている“つもり”を、一度疑ってみませんか?
それがあなたの、あたたかい人間関係を築く一歩になります。